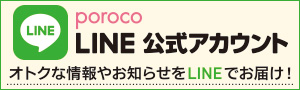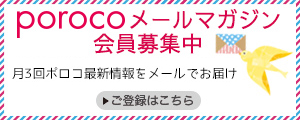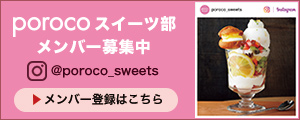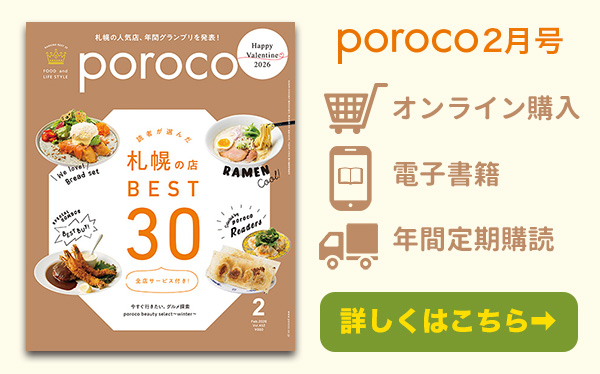【たすけてドクター(胃腸科)】019. 「機能性胃腸症」の症状と予防法は?

「機能性胃腸症」の症状と予防法は?
Q. 食事をすると胃がひどく痛むので病院に行ったところ、「機能性胃腸症」と診断されました。聞き慣れない病名だったので詳しい症状を知りたいです。また、こうした症状を引き起こさないための予防法はあるのでしょうか?
(27歳・女性)
A. 胃腸の働きのバランスが崩れることで起きる「機能性胃腸症」
「機能性胃腸症」とは、胃に潰瘍や胃炎、ガンなどの特別な病気がないのに、痛みや胸焼け、胃のもたれなどの症状を起こす状態をいいます。胃腸の働きの低下や亢進など様々なバランスの乱れによって、種々の症状が起きてくるのです。
「運動不全型」「潰瘍症状型」「逆流症状型」の3タイプに分けられる
「機能性胃腸症」は主に三つのタイプに分けられます。「運動不全型」は、胃の食べ物と胃液を混ぜて消化を行うという働きが落ちて、胃がもたれてしまう症状。消化の終わった食べ物が胃から十二指腸へ送られる速度が遅くなり、食べ物が胃に停滞する時間が長くなると、胃がもたれたり、ゲップが出ることがあるのです。二番目は「潰瘍症状型」といって、胃が過敏になり胃液が多く出てしまう症状です。胃酸が過剰に出過ぎると、胃酸が粘膜を強く刺激したり、胃を急に緊張させてしまうので、痛みを引き起こすことがあります。これはいわゆる“胃ケイレン”といわれるものです。三番目は「逆流症状型」で、胃酸が食道に逆流することによって、胸焼けや痛みを起こすもの。食べ過ぎや、食べてすぐ横になる、夜遅く食べる、前かがみの姿勢を長時間取ったあとなどになりやすいですね。
病気ではないが、日常生活の見直しは必要
特別な病気ではないので、症状がどんどん進行するという心配はありませんが、日常生活や食生活などに気をつけなければ、症状が取れにくいことが多いです。胃の働きのバランスの乱れですから、まずそのような状態にならないよう心がけることが大事。寝不足、過労、ストレスなどをためないようにすること、胃腸の働きを助けるためによく噛んで食べる、食事は腹八分まで、食事の時間をなるべく規則正しくする、などが基本です。このような注意事項を守りながら、調子がよくなるまでは症状に合った薬を服用し続けてください。